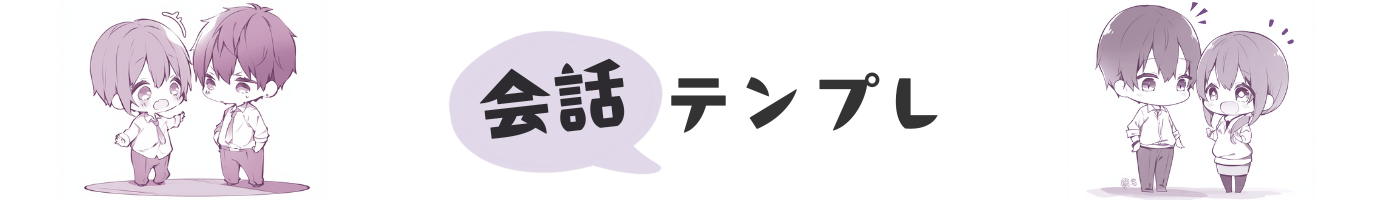クレーム対応で焦らない!謝罪メール・電話の正しい言い方と例文テンプレ集
クレーム対応の電話やメールで「どう謝ればいいか分からない」「焦って余計に怒らせてしまった」──そんな経験はありませんか?
相手が怒っている状況では、言葉を選ぶ余裕がなくなり、つい焦ってしまうものです。
しかし、クレーム対応は“言い方”次第で印象が大きく変わります。
丁寧すぎる謝罪よりも、誠実さと正確さが伝わる一言を選ぶことが大切です。
この記事では、焦らず落ち着いて対応するための
謝罪メールと電話対応の言い回しテンプレートを紹介します。
クレーム対応が苦手な方でも、この記事を読めば「相手に伝わる言葉」と「信頼を取り戻す言い方」が分かるはずです。
なぜクレーム対応で焦ってしまうのか

クレーム対応で一番多い悩みは、「焦ってしまい、うまく話せない」というもの。
電話口で相手が怒っていたり、メールで厳しい言葉を受け取ると、
「何を言えばいいのか分からない」「怒らせたらどうしよう」と、頭が真っ白になってしまう──
誰にでも起こりうる反応です。
実は、焦りの原因は「スキル不足」ではありません。
多くの場合、“感情の圧”と“マニュアル依存”によって生まれています。
感情の圧に押されてしまう
怒りの感情をぶつけられると、私たちは防衛反応として“早く終わらせたい”と感じます。
その結果、相手の話を最後まで聞かずに弁解したり、形だけの謝罪で切り上げようとしたりしてしまう。
しかし、相手は「話を聞いてもらえなかった」と感じ、さらに不満を募らせてしまいます。
つまり、焦りの正体は「怒りそのもの」ではなく、
“相手の感情を受け止めきれない自分への不安”なのです。
マニュアルに頼りすぎることで、言葉が固くなる
多くの職場には「クレーム対応マニュアル」がありますが、
それを“覚えること”に意識が向きすぎると、
実際のやり取りで柔軟に対応できなくなることがあります。
たとえば、
「このたびはご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」
という定型文を機械的に繰り返すだけでは、相手の気持ちに届きません。
マニュアルはあくまで“型”。
そこに自分の言葉を少し足して、「相手の状況を理解している」温度感を加えることが、
焦らず誠実に対応する第一歩です。
冷静さを保つには“心構え”と“伝え方の型”を持つこと
焦りを抑えるために大切なのは、「失敗しない話し方」ではなく、
“落ち着いて話せる準備”をしておくこと。
クレーム対応では、
- まず相手の感情を受け止める
- 事実を整理する
- 次の行動を約束する
──という3ステップを意識するだけで、頭が整理され、自然と焦りが減ります。
つまり、冷静さは“場数”ではなく、“準備と構え”で身につくもの。
クレーム対応で大切な3つの基本姿勢
クレーム対応では、どんなに丁寧な言葉を使っても、基本姿勢ができていないと誠実さは伝わりません。
焦って「早く謝ろう」「すぐ解決しよう」と思うほど、空回りしてしまうこともあります。
まずは、どんな状況でもぶれない3つの基本姿勢を押さえておきましょう。
① 相手の感情を受け止める(否定せずに共感を示す)
クレーム対応の第一歩は「共感」です。
怒りの感情を否定したり、論理で説明しようとする前に、
まずは「相手の気持ちを理解しています」という姿勢を示しましょう。
💬 例文
「ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」
「おっしゃる通りです。ご迷惑をおかけしてしまいました。」
この段階では“原因”よりも“気持ち”を優先することがポイント。
感情が落ち着けば、相手も冷静に話を聞いてくれるようになります。
焦って説明や弁明を挟むと、火に油を注ぐ結果になりかねません。
② 事実確認を焦らない(すぐに言い訳をしない)
クレームを受けた瞬間に、「自分のせいじゃない」「誤解です」と言ってしまうと、
相手は「責任を回避している」と感じ、さらに不信感を募らせます。
実際、クレームの多くは“情報のズレ”や“勘違い”から生じています。
だからこそ、「すぐに反応しない」ことが信頼につながる行動です。
💬 例文
「詳細を確認し、すぐにご連絡いたします。」
「事実関係を社内で確認した上で、改めてご報告いたします。」
この一言を添えるだけで、「きちんと対応してくれる人」という印象を与えられます。
“その場しのぎの言い訳”よりも、“誠実に確認する姿勢”のほうが何倍も信頼されます。
③ 早めの報告と共有(上司・関係部署へ)
クレーム対応を一人で抱え込むのは危険です。
対応が遅れたり、判断を誤ると、会社全体の信頼を損ねてしまうこともあります。
そこで大切なのが、「早めの報告・共有」です。
特に次のようなケースでは、すぐに上司へ相談するのが基本です。
- 金銭や契約に関わる内容
- 長期的な取引先・顧客からのクレーム
- 感情的に強い口調や脅迫に近い表現がある場合
💬 例文
「〇〇様からこのようなお申し出がありました。対応方針を相談させてください。」
早い段階で共有しておくと、サポート体制も整いやすく、結果的に対応もスムーズになります。
姿勢が整えば、言葉は自然と整う
クレーム対応で焦らないための基本は、
「受け止める → 確認する → 共有する」という3ステップを意識すること。
この順番を守るだけで、どんな場面でも落ち着いて話せるようになります。
謝罪の言葉は、その場の言い回しよりも、姿勢の丁寧さで伝わるもの。
焦ったときこそ、深呼吸して「まずは聞く姿勢」から始めましょう。
【例文付き】謝罪メールの正しい書き方
クレーム対応のメールは、スピードと誠実さの両立が求められます。
ただし、焦って長文になりすぎたり、謝罪の言葉を並べすぎると、
かえって「何を伝えたいのか分からない」という印象を与えてしまいます。
大切なのは、「謝罪 → 原因説明 → 再発防止 → 感謝」の流れを意識すること。
この4ステップを押さえるだけで、相手に誠意が伝わるメールになります。
① 件名は明確にする:「【お詫び】〇〇の件について」
クレーム対応メールの件名は、何よりも“分かりやすさ”が重要です。
「〇〇についてのお詫び」「ご迷惑をおかけした件」など、
一目で“謝罪メール”と分かる件名にしましょう。
💬 悪い例
件名:昨日の件について(内容が不明確で印象が弱い)
💬 良い例
件名:【お詫び】ご注文商品の誤配送について
件名:【お詫び】システム不具合に関するご報告
相手は多数のメールを受け取っています。
件名で「誠実に対応している」と伝えるだけでも、印象が大きく変わります。
② 冒頭はまず謝罪から始める
メールの最初に入れるべきは、“言い訳の前に謝罪”です。
どんな理由があっても、相手が不快な思いをした時点で、最初に謝罪するのが基本です。
💬 例文
このたびは弊社の不手際によりご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
ご指摘いただきました件につきまして、深くお詫び申し上げます。
ここではまだ原因説明を入れず、あくまで“相手の気持ち”に寄り添うことを意識しましょう。
③ 中盤で原因と現状を説明する
次に、トラブルの内容や原因を簡潔に、分かりやすく説明します。
専門用語や社内事情を並べるより、相手が理解できるレベルの表現がベストです。
💬 例文
今回の誤配送は、出荷システムの設定ミスによるものと判明いたしました。
現在は該当箇所の修正および確認作業を完了しております。
長くなりそうな場合は箇条書きにしても構いません。
重要なのは、責任をあいまいにせず、自社として対応していることを明確にすることです。
④ 結びで再発防止と感謝を伝える
最後は、再発防止の取り組みと感謝の言葉で締めます。
「今後は改善します」という意志を明確にすることで、信頼を回復しやすくなります。
💬 例文
今後は同様の事態が発生しないよう、チェック体制を強化してまいります。
このたびは貴重なご指摘をいただき、誠にありがとうございました。
実際に使えるメールテンプレート
件名:【お詫び】ご注文商品の誤配送について
〇〇株式会社 〇〇様
いつもお世話になっております。〇〇株式会社の△△でございます。
このたびは弊社の不手際によりご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
ご注文いただいた商品を誤って別のお客様に発送してしまいました。
現在は正しい商品を本日中に再発送いたしました。
今後は出荷前の確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
ご多忙のところご対応いただき、誠にありがとうございました。
--------------
〇〇株式会社 △△(氏名)
電話:XXX-XXXX-XXXX
メール:XXXX@XXXX.jp【電話対応】焦らず伝える謝罪の言い回し

メールよりも緊張しやすいのが、クレーム対応の電話です。
相手の声のトーンや勢いに飲まれ、思わず言い訳をしてしまったり、
焦って余計な一言を付け足してしまうケースも少なくありません。
しかし、電話対応では「完璧に話すこと」よりも、
声のトーン・聞き方・間の取り方を意識するだけで印象が大きく変わります。
① 声のトーンは“低め・ゆっくり”を意識
焦っていると、声が高く速くなりがちです。
けれど、怒っている相手ほど、落ち着いた声とテンポを求めています。
電話の冒頭でまずは落ち着いて、はっきりと名乗り、
“誠実に対応する姿勢”を声で伝えましょう。
💬 例文
「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の△△でございます。」
「このたびはご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」
ポイントは、「早口にならないこと」「語尾を強調しすぎないこと」。
安心感を与えるのは“ゆとりのある話し方”です。
② 言い訳より「受け止め+対応」の流れで話す
電話対応で最も多い失敗は、“説明が先に出る”ことです。
事実を伝えようとしても、相手には「言い訳」と受け取られてしまうことがあります。
まずは、相手の言葉を受け止める一言を添えましょう。
💬 NG例
「それはこちらのミスではなく…」
「実は、担当が違っておりまして…」
💬 OK例
「お言葉を真摯に受け止め、すぐに確認いたします。」
「貴重なご指摘をいただき、誠にありがとうございます。」
このように、“相手の気持ち→対応の行動”という順で話すと、
誠実さが自然に伝わります。
③ 感情的な相手への対応法
クレーム対応では、相手が強い言葉を使ってくることもあります。
そんなときほど、反論せず・遮らず・最後まで聞くことが最優先です。
💬 例文
「お話を最後まで伺います。少々お時間をいただけますか?」
相手が落ち着くまでは、事実確認や説明を挟まないほうが賢明です。
怒りが収まってから、静かに対応方針を伝えることで、
相手も「きちんと聞いてくれた」と安心します。
また、暴言や人格否定に発展した場合は、
「一度内容を整理して、改めてご連絡いたします」と伝えて切る判断も必要です。
対応者を守ることも、企業としての誠実な対応の一部です。
④ 伝え方の型を持っておくと焦らない
クレーム電話では、事前に“話す流れの型”を持っておくと、
焦らずにどんな場面にも対応できるようになります。
📞 基本の流れ
- 名乗りと謝罪
- 話を聞く(相づちで共感を示す)
- 原因確認と対応方針を伝える
- 感謝と再発防止の一言で締める
💬 例文まとめ
「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。」
「お話を伺い、すぐに社内で確認いたします。」
「今後はこのようなことが起きぬよう、改善に努めてまいります。」
クレームを“信頼回復のチャンス”に変える言葉
クレーム対応は「謝る場」ではなく、信頼を取り戻すチャンスです。
どれほど誠実に謝罪しても、最後の締め方があいまいだと、
「また起きるのでは?」という不安を残してしまいます。
逆に、謝罪の後に“改善の意志を伝える一言”を添えるだけで、
相手の印象は驚くほど変わります。
① 謝罪で終わらせず、「改善」を伝える
謝罪だけで終わると、「その場しのぎ」と受け取られがちです。
誠意を感じてもらうには、「これからどうするか」を言葉にすることが重要です。
💬 例文
「今後はこのようなことが起きぬよう、社内体制を見直しております。」
「原因を社内で共有し、再発防止の仕組みを整えております。」
こうした“改善を具体的に伝える一言”が、相手の不安を和らげ、
「ちゃんと対応してくれた会社だ」という印象を残します。
② 感謝の言葉を添えると印象がやわらぐ
クレームを「指摘してもらえた」と捉え、感謝を伝えるのも効果的です。
怒りの感情が落ち着いた後、「丁寧に対応してくれた」と感じてもらいやすくなります。
💬 例文
「ご指摘をいただき、誠にありがとうございます。改善のきっかけをいただきました。」
「お忙しい中、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。」
相手に「迷惑をかけた」という意識だけでなく、
「教えてもらえた」という前向きなトーンを持つことで、
会話の終わりが柔らかく締まります。
③ 信頼を取り戻す“締めの言葉”3パターン
最後の一言が、あなたの対応全体の印象を決めます。
下記の3パターンを状況に合わせて使い分けましょう。
パターン①:誠実に対応する姿勢を伝える
「今後は同様のことがないよう、誠心誠意対応してまいります。」
→ 相手の信頼を最優先したいときに効果的。
フォーマルで企業対応にも使える言い回し。
パターン②:迅速な対応を約束する
「本日中に対応を完了し、再発防止策を共有いたします。」
→ スピード感を示すことで、対応力を印象づけたい場合に。
パターン③:相手との関係継続を意識した締め
「今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。」
→ 長期的な取引や顧客関係を意識したビジネス向け表現。
まとめ|焦らない対応こそ信頼を生む
クレーム対応は、ただ謝るための場ではありません。
むしろ、相手の信頼を取り戻す絶好の機会です。
トラブルが起きた瞬間こそ、相手は「この人(この会社)はどう対応するか」を見ています。
だからこそ、焦らず落ち着いて、誠実さを言葉で形にすることが大切です。
メールでも電話でも、伝わるのは「テンプレ+心」のバランスです。
定型の謝罪文や言い回しを使いながらも、
その中に“あなた自身の気づかい”を一言添えるだけで、印象はまったく違います。
💬 たとえば
「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
今後はこのようなことが起きぬよう、社内体制を見直しております。」
このように、「謝罪+改善の意志」をセットで伝えることが、
“謝るだけの対応”から“信頼を生む対応”への第一歩になります。
クレーム対応で最も避けたいのは、焦って言葉を選び間違えること。
焦りは誠実さを曇らせ、冷静さは誠意をより強く伝えます。
事前に言葉の型を持っておけば、どんな相手・どんな状況でも慌てることはありません。
今日紹介したテンプレートやフレーズを使えば、
怒りの場面を“対立”ではなく“対話”に変えることができます。
💬 締めの一言
「焦らない言葉選びが、トラブルをチャンスに変える。」
丁寧な一言が、信頼を失わない最良の防波堤です。
次のクレーム対応では、ぜひこの記事の“言葉の型”を思い出してください。
それだけで、あなたの印象は確実に変わります。