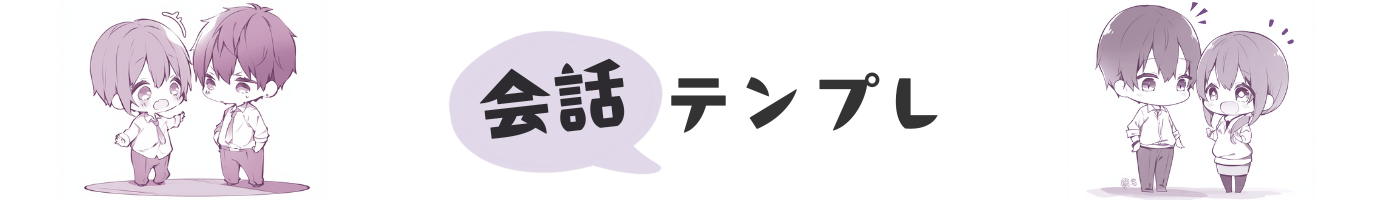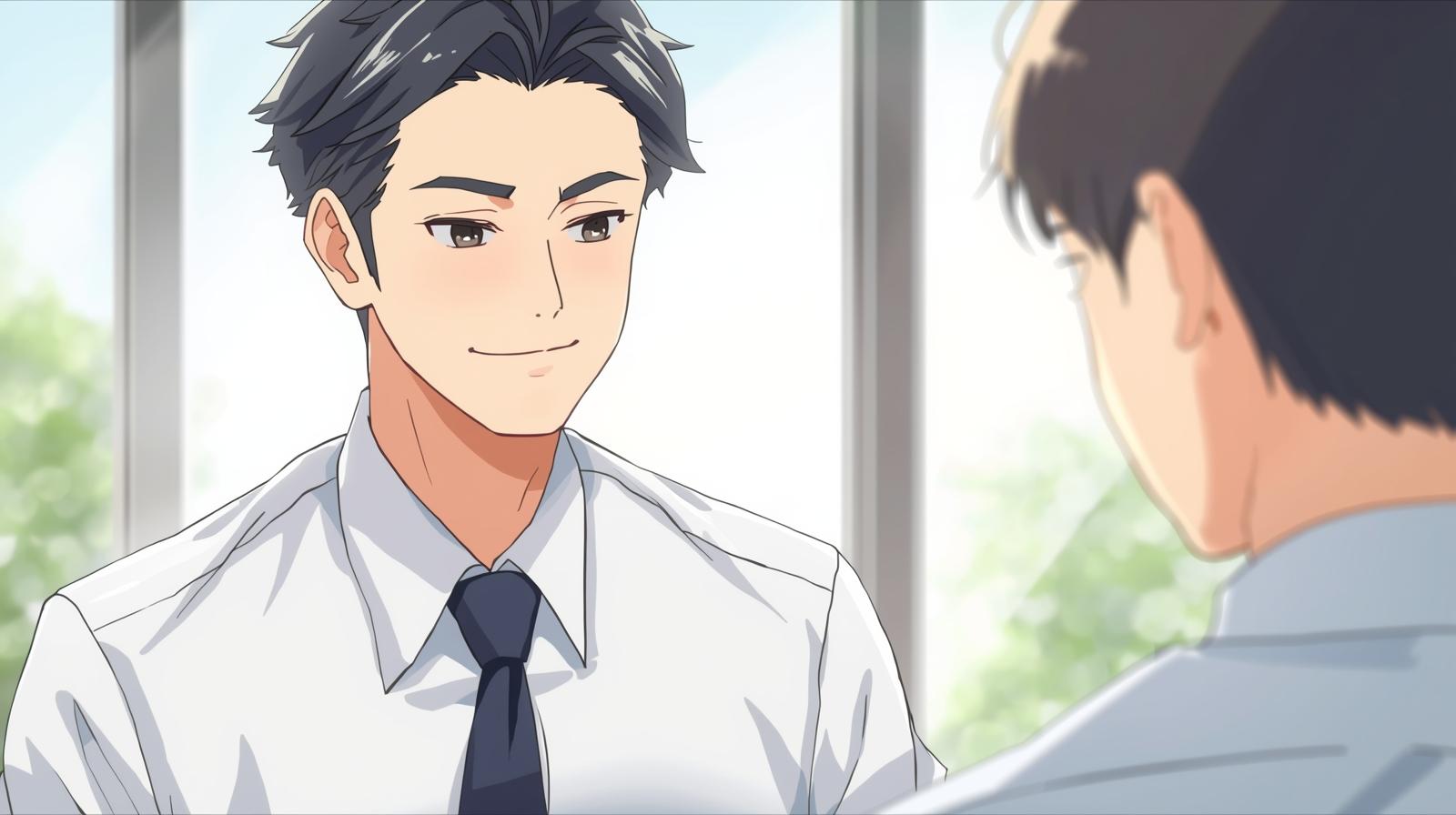部下を注意するときの言い方5選|信頼を失わない“やわらかい伝え方”例文集
部下のミスに気づいたとき、どう伝えればいいか迷った経験はありませんか?
感情のまま叱ると関係がぎくしゃくし、やさしく言いすぎると伝わらない——。
注意は、言葉一つで“信頼を築くきっかけ”にも、“心を閉ざされる原因”にもなります。
大切なのは、「責める」ではなく「育てる」姿勢で伝えること。
本記事では、角を立てずにしっかり伝わる“やわらかい言い方”を、具体例とともに紹介します。
「言いづらい」を「伝えてよかった」に変えるための、すぐ使える言葉のテンプレートです。
なぜ“注意の仕方”で信頼が変わるのか
部下を注意する場面は、実は「育てる時間」でもあります。
ところが多くの人が、「注意=怒ること」と思い込み、つい強い口調になってしまいがちです。
逆に、やさしすぎて伝わらない言い方では、改善のきっかけを失ってしまいます。
注意の本質は、相手を否定することではなく“守るための言葉”を選ぶことです。
たとえば、「ミスを責める」のではなく、「次に同じ失敗をしないように伝える」意識を持つだけで、
相手の受け取り方は大きく変わります。
人は、頭ではなく“感情”で言葉を受け取ります。
同じ内容でも「どう伝えるか」によって、信頼が生まれることもあれば、距離ができることもあるのです。
つまり、注意の仕方=信頼関係のバロメーター。
上司や先輩の一言次第で、部下は「自分を理解してくれる人」だと感じるか、「怖い人」だと感じるかが決まります。
「伝え方が9割」と言われるように、正しい言葉選びは職場の空気を左右します。
注意の前に押さえておきたい“3つの基本ポイント”を整理していきましょう。
注意の前に押さえておきたい3つのポイント

部下を注意するときに一番大切なのは、「何を言うか」よりも「どう伝えるか」。
そのためには、感情的になる前に一度立ち止まり、“伝える目的”を明確にすることが欠かせません。
ここでは、注意の前に必ず意識しておきたい3つの基本ポイントを紹介します。
① 感情ではなく“目的”で話す(怒りで言わない)
注意の目的は、相手を直すことではなく、成長を促すこと。
怒りや苛立ちをぶつけてしまうと、相手は内容よりも「怖かった」という印象だけが残ります。
伝える前に「自分は何を改善してほしいのか?」を整理すると、自然と冷静な言葉が選べます。
💬 例:「次に同じ場面があったら、こうしてみようか」
② 周囲に聞かせない(人前ではなく1対1で)
他の社員の前で注意すると、どんなにやわらかく言っても「恥をかかされた」と感じさせてしまうことがあります。
注意は、1対1で落ち着いた環境で行うのが鉄則。
本人が話しやすい雰囲気をつくることで、防衛的にならず、素直に話を受け止めてもらいやすくなります。
③ 行動を指摘し、人格は否定しない
「どうしてこんなこともできないの?」という言い方は、本人の“人間性”を攻撃する印象を与えます。
代わりに、行動や事実だけに焦点を当てて伝えることが大切です。
💬 一言例:「この部分だけ次回もう少し工夫できそうだね」
たった一言でも、「改善のチャンスを与えてくれている」と感じさせる効果があります。
怒りや焦りのまま伝えてしまうと、どんなに正しい指摘も“否定”に聞こえてしまいます。
注意の前に、目的・場所・言葉の焦点を整理しておくことで、信頼を崩さない伝え方ができるようになります。
部下を傷つけない“やわらかい言い方”5選(例文付き)

「注意=叱る」と思われがちですが、実際は伝え方次第で“支える言葉”にも変えられます。
ここでは、信頼関係を保ちながら改善を促すための“やわらかい言い方”を5つ紹介します。
どれもすぐに使える実践テンプレートです。
① 「責める」より「提案」で伝える
つい「ここがダメだったね」と言ってしまうと、相手は防御的になってしまいます。
そこで、「直して」ではなく「こうしてもらえると助かる」と“提案の形”にするだけで印象が柔らかくなります。
💬 例文:「ここを直してもらえると助かります」
👉 ポイント:相手に「一緒に改善したい」という姿勢が伝わる。
② 「前置き」でクッションを入れる
注意をいきなり伝えると、「責められた」と感じやすいもの。
まずはクッション言葉で、相手の受け止め準備を整えましょう。
💬 例文:「少し気づいた点をお伝えしてもいいかな?」
👉 ポイント:やわらかい印象を与え、話を聞いてもらいやすくなる。
③ 「あなた」ではなく「内容」に焦点を当てる
「あなたが間違えた」ではなく、「この資料のここの部分」と“事実”に焦点を当てることで、
相手を否定せずに改善点を伝えられます。
💬 例文:「この資料のここの部分、もう少し整理すると見やすくなるね」
👉 ポイント:個人攻撃にならず、内容への客観的指摘になる。
④ 「期待の言葉」を添える
注意の最後に「期待している」という一言を添えると、
相手は“信頼されている”と感じ、前向きな気持ちで改善に取り組めます。
💬 例文:「○○さんなら次はきっと大丈夫だと思うよ」
👉 ポイント:叱るより“信頼を伝える”ことでモチベーションを高める。
⑤ 「共に考える姿勢」を見せる
一方的に指摘するのではなく、「どうすればよくなるか」を一緒に考える姿勢を示すと、
相手の成長を支援するスタンスが伝わります。
💬 例文:「どうしたらもっとやりやすくなると思う?」
👉 ポイント:上からではなく“伴走する姿勢”を示せる。
NGな言い方|やる気を失わせる一言とは
どんなに正しい指摘でも、「言い方」を誤ると、相手の心に壁をつくってしまいます。
とくに部下が落ち込みやすいのは、「人格を否定された」と感じる瞬間です。
ここでは、ついやってしまいがちなNGフレーズと、その改善例を紹介します。
NG例:「なんでこんなこともできないの?」「前にも言ったよね」
このような言葉は、事実ではなく“相手の能力そのもの”を否定する印象を与えてしまいます。
受け取る側は、「自分はダメな人間だ」と感じやすくなり、ミスを恐れて挑戦しにくくなるのです。
さらに、上司との間に“萎縮の空気”が生まれ、報連相も減少する原因になります。
改善例:「ここの確認、次から一緒にやってみようか」
同じ注意でも、“一緒に解決する姿勢”を示すだけで印象は180度変わります。
相手は「責められた」ではなく「サポートしてくれている」と感じ、前向きに受け止められます。
💬 ポイント:「あなたが悪い」ではなく「次はこうしよう」に言い換えるだけで信頼が残る。
失敗を責める言葉は、相手の成長意欲を削ぎます。
一方で、「次にどう活かすか」を意識した言葉は、部下を育て、チームの雰囲気を変える力を持っています。
注意の後に信頼を取り戻すフォロー言葉
どんなにやわらかく伝えても、注意を受けた側には少なからず“落ち込み”が残るものです。
しかし、注意の後にたった一言フォローを入れるだけで、関係はぐっと良くなります。
その一言が「自分を否定されたのではなく、信頼されている」と感じさせるからです。
フォロー例:「さっきは少し厳しく言ったけど、期待してるからこそだよ」
この言葉には、「あなたを大切に思っている」「成長を見ている」というメッセージが含まれています。
注意された直後の部下は、どうしても“自信を失いがち”ですが、
フォローを入れることで「見放されていない」と安心でき、次の行動に前向きになれます。
フォローが“信頼の貯金”になる理由
人間関係は「注意」と「フォロー」のバランスで成り立ちます。
注意だけでは“恐れの関係”に、フォローを加えることで“信頼の関係”に変わります。
1回の注意で失った信頼も、フォローの積み重ねで取り戻すことができるのです。
💡 たとえば——
- 「今日はありがとう。助かったよ」
- 「前よりすごく良くなってたね」
- 「前回のこと、しっかり活かせてるね」
といった一言を添えるだけでも、相手の心に“安心感”が残ります。
注意とは「指摘して終わり」ではなく、「その後どう支えるか」までが一連の流れ。
上司や先輩がフォローの言葉をかけることで、
部下は「この人の言葉なら素直に聞ける」と信頼を取り戻していきます。
まとめ|注意は“叱る”ではなく“支える”こと
注意とは、「相手を責める時間」ではなく「相手を育てる時間」です。
同じ内容でも、言葉のトーンとタイミング次第で伝わり方は180度変わります。
感情的に叱れば距離が生まれますが、落ち着いたトーンで“支える姿勢”を見せれば、
相手は「自分を理解してくれている」と感じ、信頼が育ちます。
今日紹介した“やわらかい言い方”を意識すれば、
注意が単なる指摘ではなく、「成長を促す対話」に変わります。
そしてその積み重ねが、「安心して相談できる上司」「信頼できる先輩」という評価につながっていきます。
💬 締めの一言:「言葉を変えれば、注意は優しさに変わる」